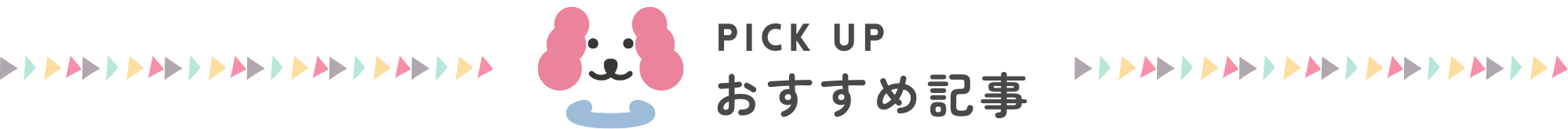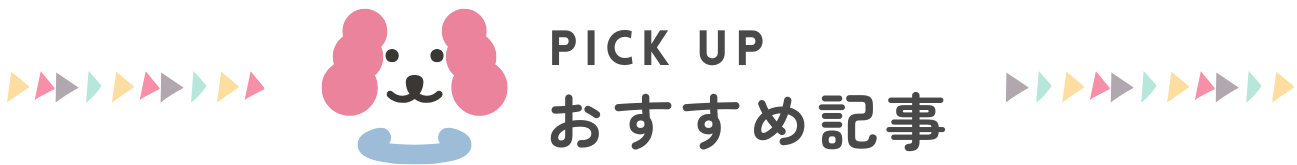犬服を選ぶ時に「ブランド問わず、サイズを統一してくれたらいいのに…」「お店によってサイズが違うから面倒」と思う方も少なくないと思います。
日本には、人間用の衣料のJIS規格はありますが、犬服に共通の基準はありません。
その理由は非常にシンプルで、犬には大きな個体差があるからです。
そのことから、サイズを犬種や体重で一括りにするのは難しいのです。
この記事では、すべての犬にフィットする服を作るのが難しい理由と背景について、詳しく解説していきます。
なぜ犬服には「共通の基準」がないの?
犬服のサイズを標準化できない最大の理由は、犬の骨格や毛量など個性の多様さです。
共通の基準を作れない理由を詳しく見ていきましょう。
① 犬種が多すぎる
世界には約340犬種、日本でも100種類以上の犬種が暮らしています。
同じ「小型犬」という分類でも、チワワやピンシャー、マルチーズやパグなど、犬種によっても体型や特徴がまったく異なるため、これらを一括りにして共通のサイズを作ることができません。
② 同じ犬種でも骨格が違う
遺伝や系統によって、同じ犬種でも骨格が大きく異なることがよくあります。
例えば、日本で人気の犬種「トイプードル」にしても
- 華奢で足が長い子
- 毛量が少ない子 or 多い子
- 筋肉質でがっちりしている子
など、個体によって体型も様々ですよね。
この子たちに同じ形の同じサイズの服を着せても、みんなにフィットするのは不可能です。
③ 毛量やトリミング前後でサイズが変わる
被毛のボリュームも大きな要因となります。
ポメラニアンやビションフリーゼなどのように毛が膨らむ犬種では、毛をカットした直後と1か月後で一回り以上サイズ感が変わってしまうことも。
被毛の量も「寸法の一部」なので、同じ犬種・同じ体型だとしても被毛量に大きく影響されます。

以前お会いしたビションフリーゼの子が、見た目10kgくらいの大きさだったのですが、体重を聞くとなんと5kgとのこと。
少し触らせていただいたら、胴体にたどり着くまでとんでもない毛の深さでした…
あの毛量を維持できるのは、お手入れの賜物ですね。
ブランド(服)ごとにサイズが違う理由
「A店ではSサイズなのに、B店ではMサイズだった」「同じショップでもこの服はMサイズ、別の服はLサイズだった」という話はよくありますよね。
いちいちサイズ表を確認しなければならず、面倒に感じる方も少なくないと思います。
ただ、これは各ブランドのコンセプトや設計思想が異なるため、仕方のないことなのです。
① 基準にしているターゲット層が異なる
ブランドごとに基準となる犬種や体格が異なります。
そのブランドがどんな犬種をターゲットにしているかを知り、自分の愛犬に合っているかを判断する必要があります。
- チワワやトイプードルが基準の場合
- 体重5kg以下程度をターゲットにしており、Lサイズでもかなり小さい
- パグやフレンチブルドッグが基準の場合
- 胸周りが広く着丈がやや短めの設計
- イタリアングレーハウンドやウィペットが基準の場合
- 全体的に細身でウエスト周りが絞られた設計
このように、それぞれで想定している基準が違うことから、「ブランドごとにサイズが違う」のです。
② デザインや素材の違い
服の形や使用している素材によってもサイズ感が異なります。
例えば、アウターとTシャツでは生地の厚みや伸縮性が違いますよね。
また、リブやゴムの有無でもフィット感は変わります。
このように数字上は同じサイズでも、デザインや生地の特性によって着用感が変わるため、服ごとにサイズを細かく設定しているブランドも多いのです。
③ パターン設計の違い
パターン(型紙)の設計によっても見た目や動きやすさが変わります。
犬服は、犬の骨格に合わせた立体的なパターンが理想ですが、人のパターンをベースとした平面的なパターンで作られている服も少なくありません。
このように、立体構造にこだわっているブランドとそうでないブランドでは、同じMサイズでも見た目の美しさやフィット感が全く違ってきます。



個人的に、犬服作りで一番難しいのはパターン設計だと思っています。
初めの頃は、立体を平面で書くことが難しくて頭の中が???ばかりでした
すべての犬に合う服が作れない理由
結論的に、たった一つのパターンですべての犬に合う服を作るのは不可能と言っても過言ではありません。
その理由を詳しく見ていきましょう。
① 骨格の違いが一番の理由
私たち人間も性別や人種によって骨格に差がありますよね。
犬は人よりも立体的な上に、人間以上に様々な骨格タイプがあります。
華奢な子やがっちりな子、胴の長さ、足の長さも個体によって大きく異なります。
同じ胴回りだとしても、着丈や袖丈、ウエストやお尻周りなどのシルエットのバランスが全く違ってきます。
そのため、一つのパターンでこれらの特徴すべてにフィットさせることはできないのです。
② 姿勢や重心の違い
犬によって立ち姿勢の角度や動きの重心も異なります。
骨格や年齢、筋肉量などによって、背中が丸みを帯びていたり胸が張っていたりと、特徴は様々です。
服は「平面の布で作る立体物」なので、あらかじめ設計した角度差がそのままフィット感の差になります。
そのため、同じ服でもシルエットに違いが出てしまいます。
③ 成長バランスと筋肉・脂肪のつき方の違い
「体重が増えた=全体が均等に大きくなる」わけではなく、胸だけ厚い、首だけ太いなど部位ごとの成長バランスが個体によって違います。
つまり、成長に応じてS→M→Lと単純に拡大しても、同じバランスのまま大きくなるわけではないこともあります。
同じ体重・サイズでも筋肉や脂肪のつき方・つく場所によって見た目が変わることも。
「同じ体重の子と同じサイズの服を着てるのに、なんか見た目が違う」みたいな現象が起きます。
④ 飼い主さんが求めるフィット感の違い
それぞれの好みや環境によって、ぴったりとしたシルエットが好きな方もいれば、少しゆるめに着せたいという方もいますよね。
犬服のパターンは数ミリ単位の違いで印象が変わるため、「どの着心地を正解にするか」という答えも一つではないのです。
つまり、物理的にも感覚的にも「一つのパターンですべてにフィットする服」は存在しないと言えます。



我が家の愛犬2匹はほぼ同じ体重・サイズですが、一方は筋肉質+小尻で、もう一方は細身+やや胴長のスタイルをしています。
同じ服を着せても、ゆとりのある部分がそれぞれ違います。
1回でぴったり合う犬服は少ない
前述した理由からも、犬服選びで「最初からジャストサイズを見つけようとする」のは、意外と難しいことなのです。
同じ犬種でも骨格や毛量などあらゆる要素が違うため、最初の1枚で完璧な服に出会える確率は低めです。
いろいろと試していく中で、愛犬に合う形や素材を見つけていく方が、犬服の知識も深まりますし、今後の選び方にも良い影響を与えてくれると思います。
とは言え、せっかく購入するのに失敗はなるべく避けたいですよね。
そんな時は、下記のことを意識して選ぶと良いでしょう。
- ブランドのターゲット層と愛犬の特徴が合っているショップ
- モデル犬が愛犬の特徴と似ているショップ
- 愛犬と同じタイプの子のレビューを参考にする
- 着丈などの部分調整に対応しているショップ



一般的な体型とは異なる犬種(フレブルやイタグレなど)は、特定犬種の専門店を利用することをおすすめします。
まとめ
犬服に明確な標準規格がないのは、犬たちそれぞれが違う個性を持っているからです。
犬服のパターンは、単純なサイズの違いではなく「骨格と動きの設計図」でもあり、人間の服以上に様々な要素が絡み合います。
そのため、一つのパターンですべての犬に合う服を作るのは物理的に不可能なのです。
だからこそ、ブランドごとに得意な犬種・特徴があり、ターゲットのニーズに合わせた設計をしています。
すべての犬に合う服は作れませんが、あなたの愛犬にぴったり合う服は必ずあるはずです。
完璧を求めたい気持ちは少しお休みして、試して比べて学びながら愛犬基準の服を見つけていくのも悪くはありません



犬服の世界は「サイズ表では見えないノウハウ」がたくさん詰まっているのです。